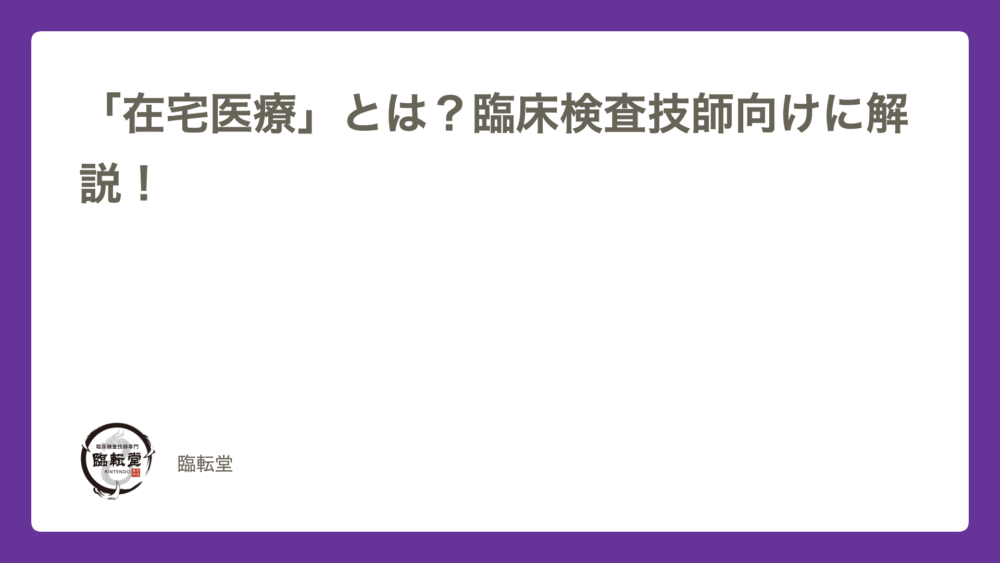日本では高齢化が急速に進み、2025年には団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者に移行することが予想されています。
厚生労働省は地域包括ケアシステムの構築や病院機能の分化を進め、住み慣れた地域で療養を続けられるように在宅医療を推進しています。こうした流れのなかで、診療所や訪問看護ステーションが患者の自宅・施設へ出向く「在宅医療」が重要な柱となりつつあり、臨床検査技師が活躍できる場も広がっています。
この記事では、臨床検査技師が現時点で在宅医療にどう関われるのか、診療報酬や機器の進歩、チーム医療とのかかわりなどを整理した上で、今後の展望について紹介します。
在宅医療の概要と現状
在宅医療は「患者が自宅や高齢者施設で医師や看護師などから医療を受ける仕組み」を指します。
訪問診療では、医師が計画的に月1回以上患者宅に訪問し診察を行うことで「在宅患者訪問診療料」や「施設入居時等医学総合管理料」を算定できます。
さらに2020年の診療報酬改定では、訪問診療時に携行型の超音波検査を実施した場合、月1回に限り400点を算定できる新設項目が盛り込まれました。このように在宅医療では検査を組み合わせることで医療機関の収益にもつながる仕組みが整ってきています。
一方で、検査そのものは医師や看護師が行うことが多く、臨床検査技師が同行して検査を担当している事例は少ないのが現状です。
2024年に開催された日本在宅医療連合学会のアンケートでは、診療所を含む153施設のうち心電図検査と超音波検査は9割以上が自施設で実施している一方、血液検査・感染症検査など検体検査は外注する割合が高いことが報告されています。また、検体検査を行う施設では看護師や医師が検査を行う割合が高く、臨床検査技師が担当する施設は病院に限られていました。
これは診療報酬の体系上、臨床検査技師が単独で訪問検査を実施しても報酬対象になりにくいことが影響しています。
現在の臨床検査技師が関われる業務
臨床検査技師が在宅医療に関わる場合、多くは在宅支援診療所や訪問看護ステーションに雇用され、医師や看護師と一緒に患者宅や施設を訪問します。
2025年の報告では、臨床検査技師が訪問診療に同行して行っている業務として以下のようなものが挙げられています。
- 機器や資材の準備・診療アシスタント:診療に必要な医療機器や検査器材の準備、訪問記録や薬袋の確認など、多職種連携の調整を行います。
- バイタルチェックと処置の補助:血圧・脈拍の測定や胃瘻・導尿チューブの交換補助、CPAPの確認、ポータブルX線撮影の補助など、診療行為のサポートをします。
- 採血や検体採取・迅速検査:血液・尿などの検体採取や血糖測定、炎症反応(CRP)検査などのPOCT(Point of Care Testing)を実施し、結果を医師に報告します。2020年改定で訪問診療時の超音波検査が保険適用になったこともあり、腹部や頸動脈などの超音波検査も担当します。
- 心電図やスパイロメトリーなど生理検査:心電図や呼吸機能検査などを行い、必要に応じてデータを解析し、医師の診断をサポートします。
- 輸血準備・在宅輸血のサポート:自宅で輸血治療を行う患者に対し、輸血準備や血液製剤の管理を行います。
これらの業務は従来病院内で臨床検査技師が行ってきた検査業務に加え、診療アシスタントや情報共有など幅広い役割を含んでいます。特にPOCT機器の進化により、血糖・血算・HbA1c・電解質・栄養・肝腎機能・炎症反応など多数の検査項目が在宅でも測定可能となり、残尿量の測定ができるポケットエコーも登場するなど、臨床検査技師の専門性を生かせる機会は増えています。
在宅医療で求められる能力と課題
臨床検査技師が在宅医療に関わる際には「何でもする」精神が必要だと指摘されています。検査だけでなく診療の補助やチーム医療の調整役として働くことが多く、患者や家族とのコミュニケーション能力や多職種との協働能力も求められます。
もう一つの課題は診療報酬制度です。
在宅医療では検査が評価されにくく、臨床検査技師が単独で検査を行う制度が整備されていないため、医師の指示のもとで実施した場合にのみ算定が認められる状況です。その結果、訪問検査の一部はボランティア的な位置づけになっています。臨床検査技師が在宅医療に参画する意義が十分に認知されるよう、検査の効果や質の向上を示すデータを蓄積し、診療報酬の改善を働きかけることが重要です。
今後の展望 – デジタル化と役割の拡大
厚生労働省は2024年の診療報酬改定において「質の高い訪問診療・訪問看護の確保」や「医療DXの推進」を重点施策として掲げており、遠隔診療やICTの活用が進められています。これに伴い、臨床検査技師の役割も変化していくと考えられます。
遠隔医療と臨床検査技師
遠隔診療では、専門医が他の医師を支援する「Doctor to Doctor (D to D)」や医師と患者をつなぐ「D to P」が一般的ですが、今後は医師と臨床検査技師が連携する「with MT(Medical Technologist)」も実現可能性があると指摘されています。遠隔超音波診断や血液検査のデータ管理を技師が担当し、現場の医師にリアルタイムでアドバイスする仕組みが広がれば、在宅医療の質が向上するでしょう。
POCTと品質管理
在宅医療では血糖やHbA1c、炎症反応などをその場で測定できるPOCT機器の活用が広がっています。しかし、POCTの意味や精度管理の重要性を十分認知している医療従事者は少なく、臨床検査技師が検体採取・保存から精度管理、データ管理まで携わるべき分野であると強調されています。今後は、POCT機器の導入指導や精度保証を担う「訪問臨床検査技師」の需要が増えるでしょう。
教育・キャリアの変革
令和4年の新しい教育カリキュラムでは、在宅医療や訪問診療の講義・実習が必須となり、学生は在宅医療現場で臨床検査技師の役割を学ぶ機会が増えています。在宅医療に関心を持つ中堅や熟練技師も増えつつあり、現場で活躍できる技術と柔軟性を身につけることが求められます。
臨床検査技師が今後携わる可能性のある分野
在宅での超音波検査の専門化
訪問診療時の超音波検査は月1回400点の診療報酬が付くため、今後は専門技師による定期的な訪問エコーが普及する可能性があります。心臓を除く腹部・血管・体表などの検査を担うことで、医師が診察に専念でき、クリニックの収益増にも貢献できます。
POCTの指導・精度管理
血糖や炎症反応などを迅速に測定するPOCTは今後も増える見込みですが、適切なキャリブレーションやデータ管理が不可欠です。臨床検査技師が教育・監督役となり、訪問看護師や医師に精度管理を指導する役割が期待されます。
遠隔検査支援
ICTを活用した遠隔超音波や遠隔検査では、現場の看護師や患者自身が検査を行い、データを専門技師が解析・評価する仕組みが考えられます。臨床検査技師は遠隔サポートの中心となり、検査の質を担保する役割を担います。
在宅輸血や透析管理
在宅輸血や在宅透析など高度な在宅医療が広がるなか、検査技師が血液製剤管理や透析液の検査に携わる場面も増えるかもしれません。安全管理と迅速な対応が求められます。
データサイエンスとAI活用
在宅で収集できる検査データは膨大になります。AIを用いた解析や異常検出、患者モニタリングシステムの開発に検査技師が関わることで、より高度な在宅医療支援が可能になります。
まとめ
在宅医療の推進により、臨床検査技師が活躍できる舞台は病院外にも広がっています。
現在は医師の指示のもと、採血やPOCT、超音波検査、心電図、機器準備など幅広い業務を担っていますが、診療報酬制度の壁や人材不足が課題です。
今後、医療DXや遠隔診療の進展、POCTの普及により、臨床検査技師の役割はますます重要になるでしょう。質の高い在宅医療を支えるために、検査技術だけでなくチーム医療の協調性やコミュニケーション能力も磨き、柔軟に新しい技術を取り入れていくことが求められます。